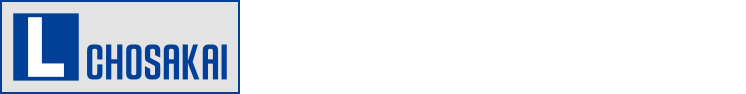労働あ・ら・かると
今月のテーマ(2013年9月)女性労働と育児休業
21世紀を境に、わが国の女性労働の在り方が変わってきた。戦後、高度成長期までの家族の理想的なパターンは、男性が外でし烈な競争を伴う仕事に従事する一方、女性は専業主婦として夫を支え、子供を学歴による競争社会に打ち勝つように導き、家事をこなす、というものであった。専業主婦世帯こそがわが国のモデルであり、女性にとっても理想像であった。この専業主婦に対しては、税や社会保険料の優遇が行われてきたし、現在もなお行われている。年金制度や健康保険についても同様である。
この基調に変化が生じた決定的な出来事は、1989年の合計特殊出生率が戦後最低を記録した、いわゆる「1.57ショック」であろう。すでに実質的に雇用市場に参入していた高学歴者を中心とする女性たちが、職場で遭遇する男性と同等の過酷な扱いによって、子供を産み育てるのが難しい、との認識が原因の一つとして広がったのである。育児休業制度は、それまでに男女雇用機会均等法によって企業の努力義務とされていたが、実効性は疑わしいものであった。そこで1991年、単独立法として育児休業法が制定された。日本を震撼させる少子高齢化による将来予測が、法の制定を後押しし、これによって働く女性が出産・育児と職業生活を両立させる、という考え方が普及することになった。育児休業法はその後も改正を重ね、たとえば2010年6月に施行された「男女が協力しつつ子育て等をしながら共に働き続けることができるような雇用環境の整備のための改正」が2010年6月から施行され、男性も子どもと親密な時間を共有できるような配慮がなされている。また、雇用保険から給付される育児休業給付金の額は、当初25%であったものが現在では50%である。
こうした結果、1990年代には、男子の雇用と無業の妻による世帯と、共働きの世帯が拮抗し始め、2012年現在では前者が787万世帯、後者が1054万世帯と、その差は開く一方となっている。
育児休業制度に見る女性労働の変化は著しいが、深刻な問題もある。それは日本の女性の標準的なライフコースにかかわる問題である。現代の若い女性にしてみれば、母親の辿ったライフコース、すなわち専業主婦が自分の例に当てはまらないなかで、他のモデル、規範を探す必要に迫られている。しかしその規範の具体化を、わが国がまだ十分に行いえていないのである。もともとこの役割を担うのは、天皇家の筈であった。現皇太子である浩宮徳仁(ひろのみやなるひと)親王は、現在国連の役職も務めている学者である。皇太子は婚姻の相手としてエリートの道を辿り、実務キャリアも豊富な雅子妃殿下と1993年に結婚した。このご夫妻による内外での幅広い「共働き」のご活躍が、日本の若い夫婦の理想のモデルとして奉られるはずであった。しかし、残念ながら周知のようにそうした結果とはならなかったし、現在もそのように動いてはいない。育児についても、愛子親王の誕生の例は、英国のウィリアム王子とキャサリン妃殿下ほどにはアピールできなかった。結論付けるならば、わが国の女性の生き方は、女性個々人の努力に一方的に期待するばかりで、政府は何ら正統性を持ったライフコースを提示できないでいるのが現状である。
育児休業制度を取得した女性の割合は、2012年現在83.7%である(雇用均等基本調査)。しかしこの数字の分母は、出産に当たって退職した女性の数を含んでいない。女性の寿(ことぶき)退社や出産退社への対応も、女性の生き方への方向性が定まらない以上、評価がばらばらの状態を示している。現政府は、21世紀の女性の理想のライフコース確立に向けて、税制や法改正の徹底化をさらに進めるべきである。
【日本大学法学部教授矢野聡】