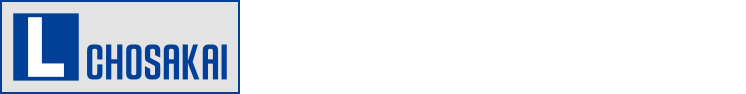労働あ・ら・かると
職業の将来
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
9月に入って職業の名称や分類について思いめぐらすことが多いと感じます。
今春改正された職業安定法の施行が段階的に施行されている真っ最中であることがその理由の一番ですが、「賃金構造基本統計調査の調査対象職種の見直しに関する意見募集について」という厚生労働省発表を目にしたり、前回の厚生労働省編職業分類表の改訂から今年で7年経過しており、その際も研究者の方々の3年近い努力を経て改訂作業が行われたことを思い出すと、そろそろその見直し作業に着手してよい頃だと思ったりすることがあるからなのでしょう。
職業分類の見直し作業の中で、その名称が整理されて「その他」の項になり、消えていった職業名があったことを想い起こすと、「これからの10年で更に消えていく職業名はどんなものなのだろうか」と思いめぐらします。
英オックスフォード大学で人工知能の研究を行うマイケル・A・オズボーン准教授は、人間が行う仕事の約半分が機械に奪われると予測しています。今後10年から20年で、アメリカの総雇用者の47%の仕事がコンピューター技術によって自動化され、その仕事(職種)がなくなるという研究です。
今回の改正の前の、大きな職業安定法改正は、1999(平成11)年に行われました。それまでは民間の職業紹介は極めて限定的な職種についてのみ取り扱うことが許されていたわけで、現在、職業紹介事業を行う旨の申請を厚生労働大臣に申請する際に、特に取扱い職種や地域を限定せずに手続きを進めると、「日本全国どこでも、全職種(港湾労働と建設現業職種を除く)取り扱える。」許可が得られることを見ると隔世の感があります。
ちなみに筆者が最初に職業紹介事業の責任者として許可を得たのは「経営管理者、科学技術者、通訳・秘書」という三職種についてでした。当時、職業紹介許可番号には取扱職種を示すカタカナが付されていて、得た許可番号は「コサツ-○○○○」というものでした。「コ=経営管理者」「サ=科学技術者」「ツ=通訳・秘書」を表す表記だったのです。
この「ツ=通訳・秘書」という職種許可は、当時外資系秘書職の求人需要に応えようとすると、必ず必要なもので、その専門性も高いものとして評価される職業でした。
しかし、9月初めの総務省の発表によれば、総務省と国立研究開発法人情報通信研究機構は、オールジャパン体制で翻訳データを集積する『翻訳バンク』なるものの運用を開始するそうです。目的は自動翻訳システムの様々な分野への対応や高精度化を進めるためとされていますので、この運用が成果を上げて自動翻訳技術の実用化・完成度が高まってくると、日本が国際的にビジネスを展開しようとするとき、外国人ビジネスパースンを雇用するときに大きな壁とされてきた「言葉と文化」のうち、少なくとも「言葉の壁」を相当低くできそうな期待感が湧いてきます。しかも実装目標は2020年としています。
しかし一方で、その職業の専門性が評価されてきた「通訳・翻訳」という職種の将来性は、なかなか厳しいものになっていくようにも思います。確かに「誰でも外国語を扱える、翻訳できる」ようになる時代は、とても便利ですし、語学力の乏しい筆者も期待するところではありますが、翻って見れば、そのことを専門性として仕事をしてきた人材にとっては、嬉しくない話かもしれません。
昭和の話になって恐縮ですが、筆者が会社員になったころは、「タイプ室」なる部署が企業内に存在し、専門学校を卒業した和文タイピストを専門職として採用して配置していました。公共職業訓練コースにも「和文タイピスト科」が設置されて職業分類表にも掲載されていたように記憶しています。
第一次石油ショックの後に「ワードプロセッサー」なるものが登場して、それから10年くらいの間に、「和文タイピスト」という熟練技能職種はみるみるその影を薄くし、求人広告などには「ワープロオペレーター」の文字が目立つようになりました。しかしその寿命もけして長くはなく、ごく少数の速記技能者を除いては「誰でも扱えるワープロ」となって、ワープロを使用することは専門性ではなくなった変化を想い起こすと、前述の自動翻訳技術の実用化は、通訳翻訳職種に対してもそうした影響を与える技術開発・進歩であるかもしれません。
類似の影響は、テレックスオペレーター職種とFAX・E-mail、自動改札機・交通カードと駅改札掛など、簡単に思いつきますし、ではこれからの十年での技術進歩と職種の盛衰を予想するとなると、ワンマン運転とホームドアの普及による電車車掌従事者の減少、書籍通販の普及と書店販売員就業者の縮小と、次から次へと例示が挙げられます。
そのような時代をこれから生きて働いていくだろう若者に必要とされる「能力研鑽」「教育訓練」学校教育の在り方についても思いを馳せてしまいます。
(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)