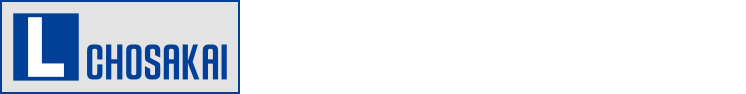労働あ・ら・かると
夏休みの観光地に見る高齢者雇用と外国人材雇用
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
「働き方改革」のこともあって、今年の夏休みは家内と東北地方の温泉巡りをしました。
そこで見たのは観光収入で地方を活性化しようとする人びとと、元気に働く高齢者、一生懸命な外国人材の姿でした。
(光景1:東京駅にて)
以前から、朝早めに東京駅の八重洲側の日本橋口を通ると、新幹線を利用する国内ツアーの待ち合わせ場所になっているらしく、旅行会社の案内人や添乗員が自社の旗を持って参加者の点呼をとっている風景をよく見ます。その人混みをかき分けて、仕事に向かうとき、何度か見かける初老の旅行会社の方がいらっしゃいます。
ご自分の会社の小旗を持ち、パンフレットを片手にキョロキョロしているツアー参加者に声をかけ、自社の企画への参加でなくともとてもスマートに案内していらっしゃいます。腰もやや曲がりかけていらっしゃいますし、失礼ながら旅行会社の派手なコーポレートカラーのシャツが似合うとはなかなか言葉に躊躇する白髪でいらっしゃるのですが、笑顔と案内のスピードが素晴らしい。筆者の推測では旅行会社で長期にわたって企画に携わった方か、ベテラン添乗員を卒業された方のように見えます。もう体力的に旅行添乗は厳しくなったのかもしれませんが、そうだとしたら、偉ぶることなく笑顔で混雑を気持ちよく誘導するこの方の現在の仕事姿は、若い時の経験と得た知見に裏付けられた素晴らしいものだと思います。政府は「70歳まで働け」とか「人生100年時代」という掛け声をかけていますが、定年後ご自分の経験を直接活かす仕事を続けられる方はそう多くはないように思える中、ほっとした笑顔を呼び起こしてくれる仕事ぶりです。
(光景2:東北の温泉旅館にて)
フロントで何か国語かを駆使して外国人観光客のチェックインを受け付けている若者、食事処で流ちょうな中国語と流ちょうな日本語を話しながら配膳接遇をしている若者が目につきました。
フロントの若者は来日して日本語学校で学んだあと、4年生大学の入試に合格して卒業し、日本での就労を希望して頑張ったそうです。この温泉旅館に就職するのに必要な在留許可を得るのに苦労したとか。これからは少し緩和されそうですが、卒業大学の専攻と就職先の職業の一致を厳しく問われたのだと思います。少なくとも筆者の見たところでは、留学中にすっかり日本が好きになり、日本で働くこと、母国からの観光客に自分の感じた日本の素晴らしさを伝えることに充分貢献しているように思えます。
今の母国には、今ほどの収入を得られる仕事はないそうですが、十年以上先の夢ではあるものの、将来は母国で外国人観光客を迎え入れて外貨を得る仕事をしたいと語る彼は、「その頃日本の資本が自分の国に進出してホテルを建ててくれたら、そこの支配人ができるかもしれない。」とも、目を輝かして語ります。
彼にとっても、日本のインバウンド収入にも、そして過疎地の温泉の活性化にも、マイナスな筈がないと思いますし、明るい未来が見えるような気さえしました。
食事処で、きれいな北京語で中国人観光客に日本の「しゃぶしゃぶ」や「刺身」の食べ方を説明し、日本人客の(余り品のない言い方で残念で恥ずかしかったですが)「お姉ちゃん、ビールもう一杯!」の注文にも応じていた女性は、台湾からインターンシップの在留資格で来日し、働いているそうです。在留期間が終わったら、台湾で人気が出始めている日本式温泉旅館に就職するよう応募しようかと言っていました。「国際交流」などという固い言葉を超えて、グローバルな視点や雇用が生まれている職場は、温泉と同様筆者の心をほぐしてくれました。
(光景3:次に宿泊した同じく東北の温泉旅館で)
温泉の脱衣場で、法被を着てきびきびと動き回っている方は、どう見ても70歳代、ニッコリ笑うと前歯が1本しかありませんでした。東北弁訛りがあり、言葉は言っていることの半分くらいしか筆者には聞き取れませんが、深く刻まれた顔のしわによる表情はとても味があって、顧客をもてなそうという気持ちが十二分に伝わってきます。
「若けぇモンがみんな都会に仕事に出ていっちまったせいで、俺ぁみたいな年寄りでも仕事がある。」という、過疎化を揶揄しているともとれる台詞ではありましたが、状況を前向きに捉えているが故の言葉なのでしょう。
食事処で食器の後片付けをしているお婆ぁちゃん(失礼!)は、「お盆に帰京する孫にやる小遣い稼ぎにもなるしね。」と明るく筆者のぶしつけな問いかけに答えてくれます。「死ぬまで働く。ピンピンコロリが一番さ。」という言葉と表情は、政府からの「70歳まで働こう!」という掛け声とは無縁に、自分の心から湧いているように見え、くつろげる夏休みでした。
各地で声をかけた日本人材・外国人材のみなさん! 無遠慮な質問に気持ちよく答えていただき、ありがとうございました。
(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)