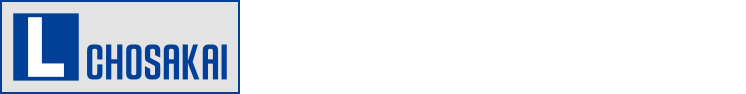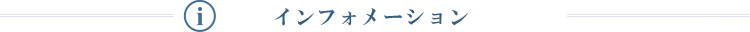労働あ・ら・かると
実質賃金3年連続マイナスの低迷 脱デフレは近い・遠い
労働評論家・産経新聞元論説委員・日本労働ペンクラブ元代表 飯田 康夫
世界の実質賃金上昇率は、17年振りの高水準 日本だけがカヤの外
〇2月下旬を迎え、2025春闘を巡る労使交渉が熱を帯びてきた。2024春闘では33年振りという高水準の賃上げ5%台が実現したものの、物価高騰の影響を受け、実質賃金はマイナス傾向で推移、2024年平均の実質賃金はマイナス0.2%と、2023年(マイナス1.0%)、2022年(マイナス2.5%)に続いて3年連続でマイナスを続けている。まさに、物価高騰で、33年振りの給与増も消費拡大につながっていない現実が描き出された。これでは脱デフレも、賃金・物価・経済の好循環の実現も容易でないことがわかる。
〇厚労省の毎月勤労統計調査(従業員5人以上の事業所)によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は、2024年1年間でみると、3月段階で高額の賃上げが実現も、翌4月の実質賃金はマイナス1.2%だった。5月もマイナス1.3%だ。33年振りの高水準の賃上げはどこに行ったというのか。それでも6月賞与月になって、ようやく実質賃金はプラス1.1%に転じ、26カ月ぶりに陽の目をみた。7月も0.3%のプラスで、実質賃金も底をついたかと思う間もなく、8月には再びマイナス0.8%に転じ、9月もマイナス0.4%、10月もマイナス0.4%、11月もマイナス0.3%と4カ月連続してマイナス。12月の賞与月になって、ようやくプラス0.6%と持ち直しが期待されるも、2024年年間ベースでは、マイナス0.2と3年続けての実質賃金マイナスとなった。
〇これを具体的な数値からみると、2024年の月平均現金給与総額は34万8,182円で、4年連続の前年比プラス。増加率は2024春闘相場の5.3%より低く、2.9%だ。この数値は4.4%増だった1991年以来高い伸び。これに対し、2024年の消費者物価指数は、3.2%上がり、実質賃金はマイナスとなったものだ。この数値は、総務庁が発表した2024年の2人以上世帯の家計調査によると、1世帯当たりの月平均消費支出が30万243円、物価変動の影響を除く実質で前年比マイナス1.1%。ここでも物価高騰の影響を受け、マイナスは2年連続。家計の消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」は28.3%で、これは1981年以来、実に43年振りの高水準だ。懐具合はいくらかアップしたものの、物価高騰の影響をうけ、消費拡大につながっていない現実が読み取れる。
〇ということは、2025春闘での課題は、実質賃金を常時、プラスに転じさせ、消費拡大への道を実現できるような、前年実績を上回る賃上げを実現し、物価高騰に負けない春闘(春答)回答書を作成することが至上命題とも言えそうだ。まさに脱デフレを掲げる政労使トップリーダーの力量が問われていると言えよう。
〇だが、帝国データバンクの調査によると、2025年の食品値上げが1万5,000点から2万点前後に達し、2024年の1万2,000点を大幅に上回りそうだとの見通しもあって、果たして実質賃金が常時、プラスに転じるのか。今、消費者を悩ませている米価高騰も備蓄米21万トン放出で、安い米価が市場に出てくるのか、買占めの噂もあり、政府の本腰を入れた米価対応も含め、物価対策の具体策の遅れが気掛かりだ。
〇果たして、2025春闘でどのような成果が生みだされるというのか。厚労省の毎月勤労統計調査や、総務庁の家計に調査に見られるように、注目したいのは実質賃金が毎月プラスに転じ、働くものの懐具合が潤わない限り、消費の拡大にはつながらないことは誰もが理解している。賃金収入がいくばくかプラスに転じても、消費購買力は容易に盛り上がらないようでは、内需拡大を通して、賃金・物価や経済との好循環の実現はできそうにないという図式が描かれる春闘だけはご免被りたいものだ。
〇脱デフレは、高額回答で、実質賃金を常時プラスに転じることで実現
〇ところで、ILO(国際労働機関)が公表した「世界賃金報告書2024‐2025年版」によると、世界の実質賃金上昇率は、前年比2.7%増と2007年の3.1%増に次ぐ上昇が見込まれ、実に17年ぶりの高水準だという。同時に、国内賃金格差は、21世紀に入って、低開発国を中心に、世界の3分の2の国で縮小していると伝える。日本の場合、春闘相場で5%台の高水準の賃上げも、全国の中小企業も含めた勤労者の給与増は平均で2.9%増では、格差はさらに広がっている事実をどう理解し、どう対処するというのか。
〇同報告書では、世界の実質賃金上昇率は、高インフレが影響した2022年に前年比0.9%減とマイナスに転じたが、2023年にはインフレが落ち着き1.8%増に。2024年には2.7%の増加が見込まれると記す。これは2007年の3.1%増に次ぐ17年ぶりの高水準で、賃金は顕著に回復していると報告書は主張する。日本だけがどうやらカヤの外に置かれているようだ。勤労者、消費者に即反応が見える政府の物価対策の不徹底なのか、指導力の欠如なのか。今日の姿をみると、政府の米価の安定化を始め、物価対策の強力な指導力が待たれるというものだ。
〇実質賃金にしろ、格差是正にしても、日本だけが置き去りにされている現実に、政労使は、どう応えるのか。マスコミ報道によると、電機、海運、金融の業績が好調で、2024年4~12期決算の上場企業の純利益合計額が最高水準となる見通しであることが、SMBC日興証券が東京証券取引所の最上位「プライム」上場企業中心に決算発表をした1269社について集計したところ純利益は前年同期比18.0%増となり、最高益の見通しだという。ただ、米国でトランプ大統領が再登板、先行き不確実性が高く、新規投資に慎重な姿勢をみせる企業もあり、不透明感は拭えない。
〇長年、日本の賃金が伸び悩んできたのは、労組の要求姿勢が生ぬるかったのか、経営陣に対してお人好しぶりが過ぎたのか、経営側の賃上げ抑制の力が強く働き、今日の低賃金横ばい時代を作り上げたのか。
〇ここ1,2年、脱デフレ、賃金・物価・経済の好循環を作り出すことに躍起となる政労使は、昨今の企業収益改善を考慮し、実質賃金を常時プラスに転じる賃上げを実現して、働くものの懐具合を潤し、消費拡大へと意識を変えさせる努力を呼び掛ける姿を打ち出すことで、願望である脱デフレに直結するのではなかろうか。経営側の春闘回答にその決意が読み取れる内容が盛り込まれるか注視していきたい。