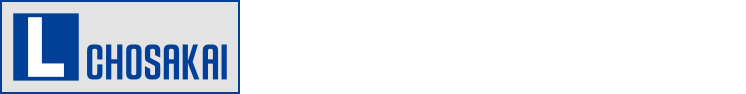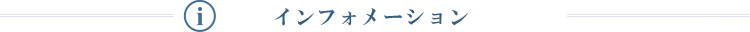労働あ・ら・かると
「私の役割」って、なんだろう?
就職・採用アナリスト 斎藤 幸江
●誰の手柄なのか?
〇現在、早くも26年新卒予定者の採用が、まっさかりである。
〇この時期の学生からの相談は、応募書類の内容や面接での回答のアドバイスが、ほとんどだ。
〇近年、特に26卒は、自分が何をしたかを説明できていないケースが多い。
〇ガクチカと呼ばれる、「学生時代に力を入れたこと」はもとより、自己PRなどで披露されるエピソードでは、「みんな」がやったことと、「本人」が手がけたことの境界が、非常に曖昧だ。
〇「サークルで、大学祭に飲食店を出店した際、新規メニューを積極的に導入しました。さらに、廃棄を減らすための仕込みの予測精度を上げて、コストも削減しました」
〇こんなエピソードが出たときは、要注意。ひとつひとつ細かく聞いていくと、実は本人の成果ではないことが、よくある。
〇「メニューの刷新は、あなたが提案したのかな? もしそうなら、提案に際して、注目した点やこだわりはある?」と聞くと、「みんなでやりました。最初は、去年のものを改善しようと言っていたのですが、話し合っているうちに、いっそのこと全部変えちゃおうという流れになりました。新たなアイデアを出したのは、後輩です」といわれる。
〇本人の役割を丁寧に聞いていくと、やっとその姿が見えてくる。
〇「一人暮らしで自炊しているので、新しいメニューについて、材料はこうすると安くできるよという案を出して、採用されました。それから、必要量についても経験に基づいて、予測を出し、予算の組み立てに役立ててもらいました」
〇等身大の本人像を掴みたかったら、エピソードに対しては、「その中であなたが果たした役割や、とった行動を具体的に説明してください」といった深掘りを勧めたい。
●叱られず、ほめられず
〇「採用側は、あなたが状況をどうとらえて、どんな行動を起こすのか。それが、周囲にどういう影響を与えるのか。そういったことを知りたい。だから、集団とあなた自身の行動を分けて考えよう」
〇そう促すと、悩んでしまう学生も多い。
〇上記ケースでは、「なるほど、みんなからそういう案が出たんだね。そのとき,あなたは、何をしたの? 発言したことはある? その発言をみんなはどう受け止めたのかな?」という投げかけをしないと、なかなか引き出せない。
〇「え? 自分とみんなを切り離すんですか? うーん、たいしたことはやってないかなぁ」と悩んでしまうのである。
〇また、自分の行動がどんな結果や成果につながったかを言及しない経験談も増えている。
〇なぜだろう? と考えているうちに、「あからさまな個人評価を避ける」という子供時代の教育環境が影響しているのでは?と感じた。
〇他人と比べて傷つくのはよくない。そういうことが起こらないようにしよう。順位付けは避けよう、人前で叱らない。ひいては、褒めるのもやめよう。
〇そんな中で生きてきた今の大学生は、「誰がどう、すごいのか」、「自分にあるもの,ないものは、何か」、「結果を出せるとは、どういうことなのか」等を考える機会が、少ないようだ。
〇みんな、今のままで十分ですよ。自分の気持ちを大切にして、前に進みましょう!
〇そう生きてきたのに、就職を前に、他人と自分を差別化する、結果を見据えて行動するといったことを求められる。そこで何をどう伝えればいいのだろう。彼らのそういった戸惑いは、予想以上に大きいと感じる。
〇中学生の時に野球部で打力の向上を買われてレギュラーになった、小学生の時に書道で賞を取った……。
〇そんな昔の経験を引いて、何を言いたいのだろう?と感じていたが、客観的に力を認められた場面が人生でそれだけしかないから選んだと考えると、腑に落ちる。
●就職へのギアチェンジは?
〇職場では、成果や結果を出すことを求められ、他人と比較される。
〇自分なりにやってきたのに、そのままではダメなのかも? どうやったら、今までの生き方と折り合いをつけながら、頑張れるのだろう?
〇入社後は、社員の方に丁寧に向き合ってもらい、必要なスキルを獲得し、成長できるようにしてほしいという就活生は多い。しかし、その本音は、緩い視野でしか見てこなかった自分を客観的に把握し、成長課題をつかむために力を貸してほしいのかもしれない。
〇客観的評価に不慣れで、戸惑いが大きいという前提で新人や就活生に向き合うと、接し方が見えてくるのでは、ないだろうか。