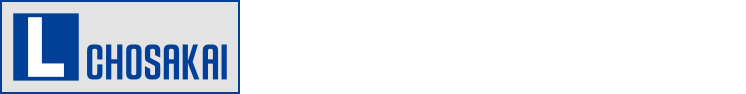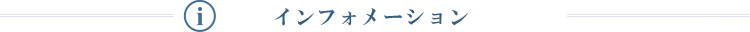労働あ・ら・かると
まもなく企業人となる若いみなさんへ 就職先企業や業界の過去を冷静に見ておこう
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
〇たいへんな就職活動を経て内定を得、来月いよいよ企業に勤務する若い人材の方々に対しては、多くの場合、賛辞や祝福、激励のメッセージが送られます。
〇筆者は敢えて今、副題に記したとおり勤務先企業の過去の負の歴史を見ようと訴えたいと思います。
〇「疑獄」と呼ばれたり、「戦後最大級の贈収賄」と報道される事件には、かかわった企業の名前や業界名が付されて何々事件というタイトルになることがありますが、同じようなことが最近次々と起こってきています。データや記録の改ざんをめぐる報道や、企業内の犯罪として横領やハラスメント(いじめ)が摘発されたとの記事も、現在進行中のもの含めて、後を絶ちません。
〇事件にその名がついた企業、不祥事が報道された企業でこれから働くみなさんは、その組織の未来をこれから担うわけですが、それには過去についての正確な知見が必要ではないでしょうか。
〇過去の疑獄事件や不祥事に関わった会社そのものに就職したのではなくても、同業界で起きた事件について、同じ業界だと同じ体質を持っている可能性があるとの視点で、自分の就職した会社ではその事件をどのように受け止めていたのか、「対岸の火事」(自社とは関係がないこととすること)、「他山の石」(自社とは関係がないようにみえても教訓とすること)のどちらだったのかを見ておくことは、これからの企業人としての人生に有益なことだと思います。
〇悲しく情けない現実ではありますが、いつの世でも欲にかられて不正に手を染める人々がいます。なぜそのような社内犯罪、非違行為を防げなかったのかというのも重要な視点です。特定の立場を利用して、自分もしくは他者に便宜を図り、見返りの金銭収受という行為は汚職です。その事件が個人の行為であるだけでなく、刑事罰の対象になることを知りながら企業として関わっていたならば、「企業ぐるみの犯罪」といわれるのも当然でしょう。
〇また、調べてみると、案外基本的な知識が欠けていて、その無知ゆえに法に触れてしまった事実を見つけることもあると思います。例えば、上場を前にしてついつい親しい友人に情報を漏らしてしまい、インサイダー取引事件になってしまった場合など、「なんでこんなことを知らずに違法行為をしてしまったのか」と思うこともあるでしょう。
〇そのような事例を発見した時には「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」ということを思い出してください。企業・会社というものは、人間一人ではできない事業を、多くの人が集まって行うためにできた組織です。誰かひとりでも「それ、まずいのでは?」「念のために顧問弁護士さんに相談したら?」と主張実践出来たら、事件を起こさずにすむ(すんだ)のではないでしょうか。「耳の痛いことを進言する」人材を、排斥せずに組織の中に置くことの重要性を忘れていなかったでしょうか?
〇もっともこの「歴史に学ぶ」というのは原文では、自分の経験だけでなく「他者の経験に学ぶ」というニュアンスもあるようです。過去の歴史だけではなく、今、同業界で起きている不祥事について「人のふり見て我が振りなおせ」ということももちろん必要でしょう。
〇過去不名誉な歴史を持つ企業に就職した新入社員の方と話すと、「それは昔の人がやったことで私は関係ない」「昔のことでしょ」という方が多数いらっしゃいます。
〇筆者が期待したいのは、その過去を教訓とし、そんなことを二度としない会社を自分たちが新たに作っていくのだという気概を持ってほしいと思うのです。
〇就職した企業の中でその残念な歴史がどのように記録され、再発防止策が実施されたかを知り、その再発防止策が今も有効に機能しているかどうかを見定めておくことは、今後のみなさんの人生で起きるであろう、様々な局面において「人として恥ずかしくない行動」をとれるかどうかにも、必ず役立つはずです。
〇まずは社内報のバックナンバーを探して目を通してください。当時の新聞記事も簡単に探せる時代です。社内と社外の情報の落差を知ることもとても大事です。
〇また労働組合のある企業に入社したのであれば、その記録も見てください。働く立場からの記事を社内報と比べるのも、興味深いことだと思います。
〇未来を本当に変えることができる一番の立場にいるのは自分たちであり 今の経営者ではないのかもしれないという発想で、社外(社会)で大きく報道された不祥事について、当時どのように受け止めたのか、その後どのように推移したのかを見てください。
〇倫理喪失の時代という残念な指摘もありますが、氾濫する真偽不明の情報に溺れるのではなく、社内の情報と社会の情報、今の勤務先の現状と過去の歴史、そのバランスを見ながら考えることが大事ではないでしょうか。
〇新社会人の方々には、自分の仕事の後(あと)工程(こうてい)を見つめて、自分が生産する製品、自分が提供するサービスを利用する人々の姿を思い浮かべて、いつも「教訓化と改善」を忘れずに日々の仕事に精進されることを望んでいます。
以上
〇(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)