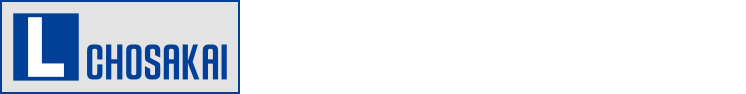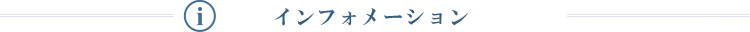労働あ・ら・かると
主要企業5%台半ばの賃上げ、課題は中小企業の賃上げだ 果たして格差是正は進んだのか、価格転嫁に難題を残す
労働評論家・産経新聞元論説委員・日本労働ペンクラブ元代表 飯田 康夫
〇2025春闘は、1か月強前の3月12日、主要大企業を中心に、満額回答など5%台から6%台という一斉集中回答が出され、マスコミを賑わせた。この回答は、2024春闘で33年ぶりに5.3%という高い賃上げが実現したが、2025春闘ではこれをさらに上回る賃上げ回答となり、浮き沈みを繰り返していた実質賃金が常時プラスに転じてくるのかに期待が高まる。果たして、政労使が求めていた賃金・物価・経済の好循環が実現し、脱デフレの社会が描き出されるのか注目していきたい。
〇一斉集中回答日翌日の3月13日付け朝刊各紙は、次のような見出しを掲げ、紙面を飾った。「賃上げ高水準で早期決着」(朝日新聞)、「春闘 賃上げ高水準 満額昨年より減る」(読売新聞)、「賃上げ『5%以上』相次ぐ」(日経新聞)、「春闘 満額回答相次ぐ 要求額超えも」(産経新聞)など、見出しをみる限り、高額回答続出の2025春闘の姿が読める。
〇だが、その一方で、「中小へ波及焦点」とか、「中小は苦しい原資確保」、「大手と格差 価格転嫁進まず」、「中小の価格転嫁道半ば」などといった見出しも踊る。
大手の高い賃上げ回答を 中小企業の賃上げに波及させたい
〇一斉集中回答を受け、マスコミ論調は、どう伝えたのか。「大手の春闘回答 中小にも賃上げの波及を」(産経新聞)、あるいは「高い賃上げ定着へ労働改革と競争進めよ」(日経新聞)、「春闘集中回答 満額を経済好循環の実現に」(読売新聞)など課題や問題点を指摘する声も聞かれる。
〇中でも、中小にも賃上げの波及を記述した論調では、「2025春闘で過去最高水準の賃上げを回答したが、イオングループがパート従業員の時給を7%超引上げるなど非正規社員の待遇を改善する動きも広がっている。高水準の賃上げの流れを、今後、労使交渉が本格化する中小企業に波及させたい。連合は、今春闘で5%以上としたが、中小企業については格差是正分1%分を含め「6%以上」とした。昨春闘では賃上げで大手との格差が広がったためだ。中小企業が人手を確保するには業績が改善していなくても賃上げせざるを得ない状況だ。発注側の大企業も取引条件の見直しに努めてほしい。中小企業が持続的な賃上げを実現するには、上昇したコストを取引価格に適正に転嫁することが欠かせない。中小企業の求めに応じて取引価格を見直す原資は親企業にはあるはずだ。賃上げを中小企業に広めるには政府による取引状況の監視を強めることも求められる。中小企業にも賃上げの流れを波及させ。個人消費を活性化させることが重要だ」と論調は説く。
〇これら以外にも、「賃上げ まだら模様」とか「賃上げ 物価高に届かず、中小の持続力課題に」、「続く物価高 賃上げは不十分」、「賃上げ高水準 自動車 中小・地域に配慮」、「上げ率想定以上 人手不足で拍車」などの見出しも目に付く。
連合集計(4月3日)第3回 17,358円、5.42%。中小も5%
〇これら回答を受けて連合は3月14日に第1回回答集計を公表。その中で、平均賃金方式で回答を引き出した760組合の加重平均額は17,828円、率にして5.46%と昨年同期を上回ったとし、300人未満の中小組合351組合も、額で14,320円、率で5.09%と前年同期を上回り、これは1992年春闘時以来、33年ぶりの5%台乗せだと評価、さらに有期・短時間・契約など非正規労働者の賃上げ額は、加重平均で時給75.39円と昨年同期を上回り、率で6.5%と一般組合員をも上回った分析。その上で、連合は「国際的に見劣りする賃金水準に加え、物価高、人材確保などを背景に“人への投資”の重要性について、労使で課題を共有した上で、足元の状況も踏まえ、交渉に真摯に応じ、社会の期待に沿った回答を決断した経営側に敬意を表する」とのコメントも公表、注目を集めた。
〇その後、4月段階を迎えて4月3日第3回回答集計を公表。その中で、賃上げ回答のあった2485組合の加重平均は17,358円、5.24%。昨年同期を上回り、300人未満の中小組合は、13,360円、率にして5.0%だとする。大手と中小との格差は是正されたとは言えそうにない。
〇中小企業やパートタイマーなど非正規労働者の賃上げが注目されていた2025春闘だったが連合第3回回答集計では加重平均で時給70.51円その引き上げ率は6.10%。この数値がこれから、どこまで高額の賃上げとなってくるのか、4月中旬から5月に掛けての本格的な労使交渉がいま熱く展開されている。
民間最大のUAゼンセンのパート賃上げ過去最高の6.53%
〇パートなどの非正規労働者の賃上げについて、小売業や外食、繊維などで構成する連合傘下最大の産別組織UAゼンセン(190万人)は、一斉集中回答翌日の3月13日、加盟組合で今春闘のパートタイムの平均賃上げ率が6.53%に達し、過去最高になったと発表した事例も特筆されよう。
〇そうした中、連合は4月4日、「2025春季生活闘争4.4中小組合支援共闘集会」を開いた。これは、4月段階から本格化する中小組合の労使交渉を支援し、先行組合の賃上げの流れを波及させ、格差是正の実現に向けた連帯の強化をはかる狙いで開いたもので、街頭アピール行動も展開、中小企業での賃上げの必要性を訴えた。その席で、連合の芳野友子中央闘争委員長(連合会長)は「2024春闘では組合員一人ひとりの取り組みが社会全体の大きなうねりをもたらし、中小企業においても過去最高の賃上げを実現することができた。が、その一方で大手企業との規模間格差が拡大し、中小企業間でも『防衛的賃上げ』にとどまった企業との格差が広がるなど新たな課題が浮き彫りとなっている。日本の雇用労働者の7割は中小企業・小規模事業所で働いている。そのため、春闘において中小組合の交渉は労働条件の底上げをはかる重要な役割を担っており、大手組合の交渉結果を社会全体に波及させるだけでなく、中小企業特有の課題に即した取り組みも求められる。特に規模間格差の是正や公正な取引環境の確保は、中小企業・小規模事業所で働く労働者の生活水準の向上だけでなく、健全で持続可能な経済の構築にも不可欠である。有期・短時間・契約で働く仲間に対する賃上げも極めて重要な課題だ。日本の労働市場では、これらの雇用形態で働く人が増えており、非正規雇用の処遇改善なくして、真の格差是正は出来ない。すべての働く者の生活向上を実現するために企業規模や雇用形態を問わず、すべての労働者の賃上げを推し進めていく必要がある。中小組合の闘いは、まさにこれからが本番だ。すべての働く者の処遇改善の実現に向けて、連合一丸となって最後まで闘い抜こう」と激を飛ばす。
〇参考までに中小組合支援に向けた決意表明の要旨をみる。
〇決意表明をしたのは、連合労働条件・中小労働委員長の神保政史氏(電機連合会長)で、要旨、次のように述べた。
〇「今後の中小組合の交渉では中小企業労働者及び有期・短時間契約等で働く労働者を含め、これまで以上にすべての働く者の月例賃金の改善と『人への投資』に拘った交渉を粘り強く進め、要求の主旨に沿った最大限の回答引き出しにつとめてほしい。また、適正な価格転嫁についても、親会社や発注側企業に対する価格交渉の進捗について『取引適正化・価格転嫁に関するチェックリスト』を活用しながら労使で真摯に話し合ってほしい。連合‣構成組織・地方連合会がそれぞれの役割を果たし、中小組合の交渉をサポートし、交渉環境の醸成や地場相場の形成と波及につとめ、賃上げの流れを連合組織内のみならず、労働組合のない職場で働く仲間も含めて賃上げの流れを社会全体に広げていくことに全力を尽くす」と熱く語った。
〇それに先立ち、連合は、中小企業関連の経営者団体と意欲的な労使交渉を重ねてきた。
〇その先陣を切ったのが日本商工会議所(日商)との懇談会だ。2025春闘での一斉集中回答日5日前の3月7日、持続的賃上げ、価格転嫁、人手不足への対応について、継続的な中小企業での賃上げの重要性を訴え、経営側の日商も「2025春闘は重要だ。地方の中小・小規模企業も含めた社会全体の賃上げが必要だ」と呼応し、「日商としても全国の企業に賃上げを働きかける」と語り、「賃上げ原資の確保には中小企業自らの自己改革による付加価値向上と共に価格転嫁の商習慣化が重要だ」と指摘。
〇日商に続いて、一斉集中回答2日前には、中小企業家同友会全国協議会とも意見交換会を開き、共同談話をもとに中小・小規模事業者の公正取引と持続的な賃上げできる環境整備に向けて両組織が連携し、力を合わせて取り組むことを確認。一斉集中回答日9日後の3月21日には、全国中小企業団体中央会との懇談会を開き、共同談話をもとに、両組織が同じ目的を持ち、力を合わせて中小企業の賃上げに取り組むことを確認するなど、労使が手を携えて中小・小規模企業の賃上げに取り組むなど意欲的な姿勢をみせた。
〇中小企業の賃上げを巡っては、2025春闘一斉集中回答日となった3月12日の朝、総理官邸で政労使の意見交換会が開かれ、集中回答を目前に今後の中小企業や小規模企業の賃金交渉に向けて労使の意見交換が交わされた。席上、石破首相は「力強い賃上げの定着に向けて多くの企業で高い水準の回答がみられる。昨年11月の政労使の意見交換で大幅な賃上げへの協力をお願いした。賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現に向けた機運が高まり、実を結んできたと考える。一方で、中小企業経営者から労務費の価格転嫁や生産性向上への支援のさらなる強化が必要だと聞く。価格転嫁については、協議に応じない一方的な価格決定の禁止などを盛り込んだ下請代金法と下請振興法の改正を検討中だ」(今国会で審議中)と語り、この4月14日には中小企業の賃上げに向け、16年ぶりの自公・連合の政労会見も開かれたばかり。この場で、政府筋から中小企業政策の強化が語られ、席上、首相は「賃上げこそが成長戦略の要で、物価上昇に負けない賃上げを早急に実現、定着させていく」と強調、注目された。
持続的な賃上げの流れを 中小組合・社会全体へ!
〇締めとして、連合の芳野友子会長が3月12日集中回答を受け、翌3月13日に出したコメントの要旨を紹介し、中小企業の賃上げ実現への期待としたい。
〇連合は、すべての働く人の持続的な生活向上を図り、新たなステージの定着をめざす方針を掲げた。物価高による組合員の家計への影響、人手不足による現場の負担増などを踏まえ、賃上げ要求は6%を上回った。先行組合回答を引き出すヤマ場に向け、最大限の回答引き出しに全力を挙げるとし、総力を挙げて後に続く組合の交渉環境を支え、同時に労組のない企業の賃上げに向けた世論醸成に取り組むことを確認。その結果、幅広い産業の労組が要求の趣旨に沿った回答を引き出した。
〇多くの組合が昨年に引き続き高い水準の賃上げを獲得。これは労使が賃金・経済・物価を安定した巡行軌道に乗せる正念場であるとの共通認識のもと、企業の持続的成長、日本全体の生産性向上につながる“人への投資”の重要性について、中長期的視点を持って粘り強く真摯に交渉した結果である。先行組合が引き出した回答内容を中小組合、組合のない職場へと波及させていくことで、すべての働く者の生活向上につなげていかなければならない。
〇3月12日の政労使の意見交換の場で、中小企業や労組のない職場で働く者を含むみんなの生活向上につながる「賃上げが当たり前の社会」を実現する重要性を訴えた。石破首相は、「今後の中小企業や小規模企業の賃上げに向け、政策を総動員する」と述べた。連合は、これから労使交渉が本格化する中堅・中小組合が最大限の回答を引き出し、早期に解決できるよう構成組織・地方連合会と一体となってサポートしていく。