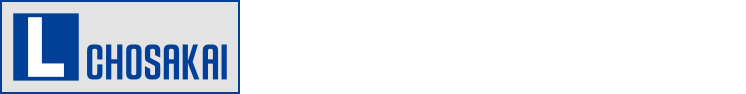労働あ・ら・かると
今月のテーマ(2013年9月 その2)2020年パラリンピック東京開催決定と障害者の雇用環境整備
9月8日の早朝、2020年のオリンピック・パラリンピック東京開催決定の知らせが飛び込んできました。
東京上空を自衛隊機がアクロバット飛行で五色の輪を描き、多くの戦争経験世代が「あの敗戦からよくここまで来た。」と感涙にむせんだ1964年の東京オリンピックの記憶がよみがえった読者の方も多いと思います。その記憶を持つ団塊世代の私は、様々な感慨や想い出の中でこの報道を受けとめました。
たまたま今年6月に公布された「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の内容を読み返していた私ですが、1964年にも東京オリンピック開催の翌月に、日本人身体障害者の国内大会と国際ストーク・マンデビル(第二次世界大戦で脊髄を損傷した軍人のリハビリ専門科のあったイギリスの病院名)競技大会(車椅子競技大会)との2部構成の障害者スポーツ大会が開催されたことを思い出しました。これは現在「第2回パラリンピック」と呼ばれていますが、筆者には当時「パラリンピック」という呼称があったとの記憶はありません。
ローマオリンピックで「裸足の王者」と呼ばれ、1964年東京オリンピックでマラソンの二連覇の偉業を成し遂げたエチオピアのアベベ選手は、その後交通事故により下半身不随となりましたが、前述のストーク・マンデビル病院に入院してリハビリを受け、この間、病院で開かれたストーク・マンデビル競技大会に参加したと伝えられています。
今回の誘致最終プレゼンテーターのひとりを務めた、気仙沼出身の佐藤真海選手は、かつてこんなことを言っていました。「自分はパラリンピックに救われてきた。19歳の時に骨肉腫で足を失って、将来が本当に見えなくなったけれど、スポーツに支えられて、弱い心を強くしてくれた。」彼女の言葉は、障害を持つ方々だけではなく、健常者にとっても、また遅々として進まない復興途上にある気仙沼の津波被害者の方々にも深く響いたことは間違いないと思います。
私の関わる人材紹介業界においても、北京パラリンピック出場者、ロンドンパラリンピック柔道解説者である初瀬勇輔氏による人材紹介会社が誕生し、代表者である彼が「障害者人材を紹介するだけでなく、障害者雇用をマネジメントできる健常者も紹介したい。」と抱負を語っています(株式会社ユニバーサルスタイル)。
一歩一歩努力することが、56年前に比べての大きな進歩につながっていることが実感できます。
障害者雇用を進めていく根底には「共生社会」実現の理念があり、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するためには、職業による自立を進めることが重要であることは言うまでもありません。障害者法定雇用率が今年4月から2.0%に引き上げられたこともあり、障害者雇用を促進しようとする企業の採用担当者の方々のご苦労は多々あると思いますが、その一つに「通勤環境」があると聞きます。自社の事業場内の設備を、コストをかけて一生懸命障害者の方の勤務環境を整えても、勤務先に到着するまでの通勤環境の未整備のせいで、就業を断念される障害者の方もいらっしゃるとのことです。
老朽化の問題が指摘されているとはいえ、現在の東京の社会基盤が、国立競技場や駒沢競技場などのスポーツ施設に限らず、拡幅された一般道路、首都高速道路、ホテル等をはじめとして、1964年東京オリンピックの時に整備されたものをベースとして50年以上利用しているわけですから、7年後の2020年オリンピックに向けての設備投資に当たっては、2070年までは最低使えるユニバーサルデザイン設備をという視野をもってインフラ整備を行って欲しいものです。
そうすれば、障害者の方が仕事をしやすい、街に出かけやすい21世紀東京モデルが出現することでしょうし、それが、少子高齢化社会が更に進むその後の日本の社会基盤として機能してくれれば、障害の有無にかかわらず暮らしやすい円熟都市を実現できると夢見ます。
もちろん一方で、オリンピックの歴史が戦争の歴史と無縁だったわけではなく、1940年の東京オリンピックは開催が決定したにもかかわらず、太平洋戦争への足取りの中、開催を返上することになったことを忘れてはなりません。今、現在戦争の悲惨の下にある人びとが7年後には戦争が終わり、「平和の祭典」であるオリンピックに参加することができることを願う気持ちも忘れずにいたいと思っています。
(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)
【岸健二一般社団法人 日本人材紹介事業協会相談室長】